受け継がれるバトンの魅力
私が星湖舎(せいこしゃ)という出版社を大阪で立ち上げたのは、1999年7月20日、海の日のことであった。それから20年以上が経った。
設立当初は自分史がブームで、生きた証を残しておきたいという人たちの本を出版していた。
19歳で白血病を患った平美樹さんと知り合ったのは2003年の秋である。心不全のために、点滴だけでなく補助人工心臓の管ともつながれていた彼女は、闘病記を書いて出版することが生きる希望だった。
翌年3月に完成した『病院を出よう! ~ネコの脱出奮闘記』(星湖舎)の中には、病気がわかった時の辛さ、なんとしてでも元気になって退院したいという入院中の強い思いが綴られている。
その彼女がベッドの中で抱きしめていたのが、ジャーナリストの千葉敦子さんの闘病記『乳ガンなんかに敗けられない』(文藝春秋、1981年)だった。
闘病中の患者が先輩がん患者の闘病記を読み、今度は自分の体験を書き記して後輩たちへ伝える、まるで命のバトンのように受け継がれる闘病記。その魅力を私が知り、闘病記にほれ込むきっかけとなったのは、まさに平さんとの出会いからであった。
忘れられない来場者の言葉
それから私は数多くの闘病記を出版するかたわら、自社の本だけではなく他社から出版される闘病記も診断し、良質な闘病記を普及させるために闘病記フェスティバルやフォーラム、講演会などを開催してきた。
闘病記フェスティバルは、2017年からゴールデンウィークや8月などに、大阪・上本町の近鉄百貨店の文化サロンで開いている。「まえをむいて生きる」などと、毎回テーマを決めて、18年に2回、19年に1回と、これまでに4回を重ねた。がんに限らず闘病記を400冊ぐらい展示するほか、講演やワークショップなども行う。
「闘病を支える力」をテーマにした2018年10月の第3回闘病記フェスティバルでは、忘れられない言葉を来場者からいただいた。
「私が子宮の病気になった20数年前には、読みたかったけれど闘病記がなかった。でも今はたくさんの闘病記が出ていますよね。すごく患者さんの励みになると思います」
 第3回闘病記フェスティバルの様子。本は自由に手に取れる。
第3回闘病記フェスティバルの様子。本は自由に手に取れる。
闘病記を読む2つの意義
この言葉には、がん患者やその家族が闘病記を読むことの意義が2つ含まれている。
一つは闘病記から励みを得るということ。闘病記の著者は貴重な自分の体験を、同じ病気に直面する患者やその家族に役立ててほしいという思いで書く。そこには、人生を前向きに生きようとする一人の人間の強い意志がある。その意志を読み取ることで、苦しい闘病生活への励みや生きる勇気を得られるのだ。
もう一つは、がん患者や家族が本当に知りたいと思っていること、つまり病気とどのように向き合いどのように生きていけばよいのか、医師や看護師など医療従事者からは伝わってこない本音の情報が得られるということだ。
例えば、症状が深刻化した時に治療方法をどう選択したのか、そして、その結果はどうだったのか。あるいは、退院後はどのような暮らしをしたのか。家族は本人とどのように接したのか。再発や転移、副作用の不安とどう向き合ったのか。
さらには、医師や看護師とどのようなコミュニケーションをはかればよかったのかなど、体験者にしかわかり得ない情報が記されている。
それらを求めて、がん患者や家族は闘病記を読みたいと思うのだ。闘病記にはそのような役割と価値がある。



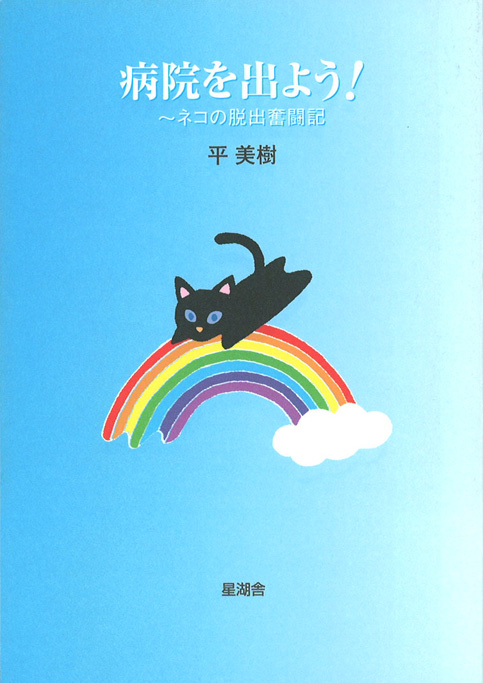
 「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内
「JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025」サイトオープンのご案内 【申込受付中】がんアドボケートセミナー2025 ~日本のがんを取りまく問題に、がん患者・家族が深くかかわることができる社会をめざして~
【申込受付中】がんアドボケートセミナー2025 ~日本のがんを取りまく問題に、がん患者・家族が深くかかわることができる社会をめざして~ 【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ
【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定
2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定





