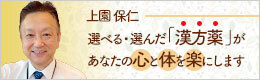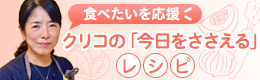つい先日、全国のがん患者会でつくる団体が、「小児とAYA世代のがん患者の妊孕性温存への支援を求める要望書」を厚生労働省へ出したというニュースがありました。

「妊孕性」。なじみのない漢字ですよね。 「にんようせい」と読み、妊娠する力を意味します。
がん治療が生殖機能に影響して、この妊孕性が低下したり、失われたりすることがあり、小児やAYA世代(15歳~39歳)のがん患者の治療における大きな課題になっているのです。
実は妊孕性の問題は、この世代だけの問題ではありません。
「妊娠できなくなるなんて、誰も教えてくれなかった……」。怒りや悲しみ、絶望感などがあふれて、泣きながらホットラインに相談してこられた女性がいます。
40代以降の方でしたが、周りから実年齢より若く見られ、自分でも「まだまだ若い」という感覚だったそうです。高齢出産が増えているというニュースも耳にしていて、自分も当たり前のように妊娠できると思っていたといいます。
しかし、乳がん手術後のホルモン療法が始まった時、少なくとも治療期間の5年間は妊娠できないと知り、愕然としたそうです。治療を終えた頃には、妊娠が難しい年齢になっているからでした。
担当医に「なぜ治療を始める前に教えてくれなかったんですか」と聞くと、「え? 出産は無理な年齢でしょ」という一言だったそうです。こうした例は少なくありません。
いまは40代以降でも子どもを持ちたいと思う方がたくさんいます。医療者が一方的に妊孕性は関係ないと決めつけず、患者さんの年齢に関わらず希望を聞き、適切な情報を伝えることが重要です。
また、患者さん自身も、治療を選択する際、もし子どもを持ちたいと希望しているなら、担当医にはっきり伝えることが大切です。

「そんな話、聞いていなかった」「こんなはずじゃなかった」と後悔のないように、医療者や家族とよく話し合いましょう。
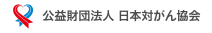


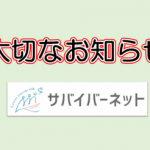 【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ
【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定
2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定 クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え
クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性
村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性