ひっくり返された本箱
2007年2月11日、長野県の軽井沢でマラソンのトレーニング中、凍った路面に滑り右足を骨折する。東京慈恵会医科大学附属病院の整形外科で手術を受けた。ゴールドマンサックスに勤めていた著者、42歳の時のことだった。
2週間が経って1回目のギブス交換の日がくる。しかし、なかなか平熱まで下がらない。3月8日夜、寝つけないベッドの中で、睾丸(こうがん)の大きさが左右で全く違うことに気づく。右側が小石のように小さくなっていたのだ。
翌日の回診でそのことを告げると、泌尿器科の外来へすぐに行くように指示される。検査の結果、腫瘍マーカーのAFPの値が23もあり、画像検査上も精巣腫瘍と判断された。
3月16日、摘出手術をし、病理検査の結果、胎児性がん、セミノーマ(精上皮腫)、卵黄囊腫の3種類のがん細胞が見つかった。
3月20日、退院を3日後に控えていたがカンファレンス室に呼ばれた。そこで主治医からがんが腹部、肺、首にまで転移していることを告げられる。ステージⅢ-bだった。 「転移の告知は、最初のガンの告知とは比べものにならないほど、衝撃的だ。凍りつくと言うか、これまで感じたことのない本当の恐怖が降りかかった瞬間だった」と、その時の心境を明かす。
一旦退院し、息子の小学校入学式を見届けて再入院し、抗がん剤治療を受ける。BEP療法と呼ばれるもので、ブレオマイシン、シスプラチン、エトポシドの3種類の抗がん剤を投与することになった。

当時の混乱した頭の状態を、著者は「ひっくり返された本棚」と表現する。がん治療のことだけではなく、子供たちの養育のこと、取りかかっている仕事のことなどが「目の前に、あらゆる本が散らばっているように、課題がいっぱい散乱していて、どれから手をつけていいのかわからない。やっかいなのは、それぞれが個別の問題ではなく、みな関係し合っていることだ」と。
間質性肺炎を発症
抗がん剤の副作用に悩まされながらも、無事に第3クール(21日間×3)を終えようとしていた。
精巣腫瘍が進行した患者の多くは、治療効果確認のため後腹膜リンパ節郭清術を受ける。著者も8月8日に、15時間に及ぶ同手術を受けた。取り出した47個のリンパ節はすべてがんの壊死組織と判明、寛解を告げられた。
だが、その2カ月前に著者は、もう1つの病気、間質性肺炎を発症していたのだ。抗がん剤が原因で、すぐさまステロイド治療を受けることになった。それはがん治療が終わり退院してからも続くことになる。
10月26日の夜には自宅の風呂場で、呼吸器の発作で倒れる。治療法をステロイド・パルス療法に切り替え、免疫抑制剤も併用された。1週間後、ようやく肺全体に広がっていた真っ白な影は薄らいでいった。
2009年、間質性肺炎は順調に治っていき、夏には免疫抑制剤の服用が終わり、10月にはステロイド薬もゼロとなった。
マラソンに挑戦するわけ
著者にはマラソンという趣味がある。ある時、得意先の部長からホノルルマラソンに誘われたのがきっかけだ。
参加が決まると、時々皇居ランニングコースを走るようになった。さらに練習を重ね、ついに本番を4時間10分で完走した。その自信からマラソンの虜になり、次々とフルマラソンの大会に参加していく。
39歳になった2003年、あるランニング雑誌でサロマ湖100㎞ウルトラマラソンの広告を目にする。40歳を迎える前に納得した走りをしたかった著者は、そのウルトラマラソンに飛びつく。それからは自己記録の更新を目指して、毎年参加することになる。

そして、5回目の参加を目前にして、がんが襲いかかる。治療中に掲げた大きな夢が、ウルトラマラソン復帰だった。
寛解から3年後の2010年9月12日、著者は第4回八ヶ岳縄文の里マラソンのハーフマラソンの部に参加した。結果はビリだったが完走した。マラソン人生の再挑戦の始まりだった。再発の可能性を意識しながらも、次々とハーフマラソン、フルマラソンに参加し、ついに2013年6月30日、第28回サロマ湖100㎞ウルトラマラソンのスタートラインに立った。
「治療こそ終えているが、私はまだ患者なのだ」という意識があった。「『もう、俺、だめなのかな……』と何度も思った。そんな意気地なしの自分を否定するために走る」と理由を語る。
そして著者は、走りながら、これまでの人生を振り返った。 「私はある時から、ガンになってよかった、間質性肺炎になってよかった、と思うようになった。病気で失ったものより得たもののほうが、遙かに大きいと感じたからだ」
「希望」「仲間」「体験情報」を届ける
単行本から5年後に出版された文庫本には、「文庫本あとがき」と作家・三浦しをん氏による「解説」が加わっている。
そのあとがきによると、主治医の依頼で、入院病棟を訪問してがん患者を励ますという、新たな役目を担うことになったそうだ。
引き受けた理由は、自身の体験から、がん患者には「希望」「仲間」「体験情報」の3つが必要と感じていたからだ。特に、がん治療の時にほしかったものは、「ガンの後、元気に社会に戻った人たちの情報」と、「ガン経験者に相談できる仕組み」の2つだった。
その2つを具現化するため、「5years」というウエブサイトを作った。登録がん患者数1万人を超える患者支援団体となった(2020年12月時点)。
ある時「弱い人はどうすればいいのでしょうか?」と質問された。その時はうまく答えられなかったが、自分を評価するのに強いとか弱いとかではなく、何とかしたいと自分なりにもがき、一生懸命であればそれでいいと、今では答えられる。弱いと感じる時にこそ、自分に価値を見いだしてほしい、と願う。
一方、マラソンは、ウルトラマラソンに毎年参加し、さらには2019年4月5日、サハラ砂漠250㎞マラソンに参加したそうだ。
いつしか読者も伴走している
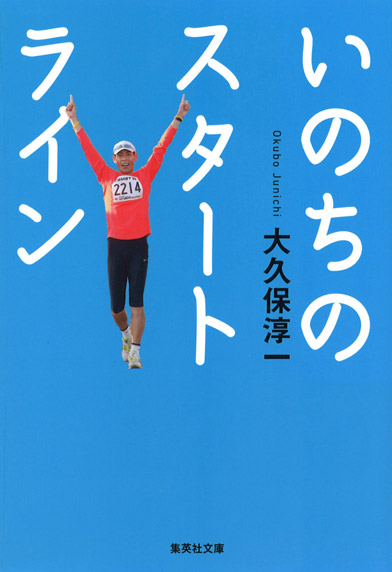
文庫本:大久保淳一著『いのちのスタートライン』2020年12月25日 株式会社集英社 定価:本体640円+税
子供たちにとって、がんになる前は忙しく働いて、とんがった顔をしたパパだった。退院後は息子と娘が、小学校から帰ってくるのをいつも待っているパパになった。そんなある時、娘から「パパ、優しい顔になったね」といわれた。働けない、ふがいない父親と思い込んでいたのに、意外にも深く愛されていることを知った。
妻は、洗い立てのパジャマをいつも病院に届けてくれていた。抗がん剤に怯えた時には励まされ、マラソンに復帰することには大反対だったのに、インターネットでのレース状況サービスに「いけー」とか「がんばれ!」といったコメントを書き残してくれていた。
医療に対しては、怒りや混乱した気持ちを包み隠さず露わに書いている部分もあり、読者は驚かされる。しかし、どんなに打ちのめされても決してあきらめない著者の姿に、読者は生きる勇気を与えられ、いつしか自身が夢と希望を失わない伴走者となって、著者と一緒に走っていることに気づくことになるであろう。



 【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ
【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定
2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定 クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え
クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性
村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性





