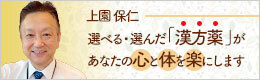この連載の第7回で、両立支援で大事なこととして「制度と風土」を取り上げました。その中で、私は「制度よりも風土が、仕組みよりも対話が大切だ」と書きました。
今回はこれに関連し、「対話」の重要性について、少し違う角度から改めて考えてみましょう。
「対話」と何か
一般的に「対話」は「会話」とは意味合いが異なると言われています。「会話」は明確な目的やゴールがない、普段のおしゃべり等を指すのに対し、「対話」は何らかのテーマに基づき、お互いの違いにも気づきながら理解や認識を深めるコミュニケーションとされています。
こうした「対話」は、意見や立場を異にする関係においては極めて重要です。医療の領域を見た場合、医療者と患者が「対話」を行うためには医療者が敷居を下げ、患者が遠慮なく話をできるような環境づくりも大切です。
また、企業では今日、育児や介護、病気の治療等を含めて様々な事情を抱えた社員も少なくありません。こうした社員が負い目や遠慮なく、「対話」を通じて自分たちの働きやすさや働きがいに関する話ができることも重要でしょう。
私が勤務するサッポロビールでは、がんを経験した当事者同士の「対話」の場として、がん経験者の社内コミュニティを立上げ、ピアサポートを実践している他、メンバーたちが参画して「両立支援ガイドブック」の改定を行ったりしています。

様々な場や形での「対話」
翻って世間を見ると、当事者との「対話」なしに大事な制度を改定しようとする動きもあったりします。制度の趣旨は何なのか、制度が実際にどのように使われているかを当事者の声を聴くことなしに改定することは、決してあってはならないことです。
今回、改定の動きを止めた人たちの行動には心から敬意を表します。その大きな力になったのは、署名もさることながら、アンケートによる3,623名もの悲痛かつ切実な声だったと、私は感じています。アンケート、それは問いを投げかけ、真摯に問いに答える「対話」そのものではないでしょうか。幾重にも織り成された「対話」による声が今回の動きを止める力になったような気がします。
何も大きな話だけではありません。私たちが働く身の回りにおいても、働きやすさや働きがいを維持向上させていく上でも、「対話」はなくてはならない大切なものです。
「私たちのことを私たち抜きで決めないで」。日本も署名、批准した国連の「障害者権利条約」が作成された際の当事者たちの合言葉です。この言葉は、何も障害に限った話ではなく、病気の治療や、育児・介護等の事情を抱える人、さらには企業や組織で働く一人ひとりにも通じるものでしょう。
あなたの身の回りでは、どうでしょうか。何も喧嘩腰になったり、怯えたりする必要はまったくありませんが、きちんと意思を伝えること、耳を傾けることが行われているでしょうか。
世間を見渡す中、「対話」の重要性を再認識する昨今です。


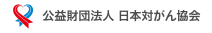


 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性
村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定
2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定 クリコ流ふわふわ介護ごはん第40回 春めく3月♪ 軽やかに新生活をスタート
クリコ流ふわふわ介護ごはん第40回 春めく3月♪ 軽やかに新生活をスタート