全国約400のがん診療連携拠点病院には、「がん相談支援センター」がある。だが、愛媛県松山市の国立病院機構「四国がんセンター」は、それに加えて、患者・家族総合支援センター「暖だん」を擁している。暖だんは、方言で「ありがとう」という意味で、「がんになっても安心して暮らしていける地域社会の実現」を目指す。病院棟から独立した建物を訪れると、家庭のような世界が広がっていた。
(文・写真 日本対がん協会 中村智志)
暖だんの「憩いのひろば」にある黒いマッサージチェアで体をほぐしていた男性が、満足そうに歩いてきた。
思わず、谷水正人(まさひと)・四国がんセンター院長へのインタビューを中断して声をかけた。
「気持ちよさそうですね」
「ええ。毎日? いや毎日やないけど、来られるときに来ます」
男性は玄関口で女性スタッフに「ありがとうございます」とお礼してから、帰っていった。谷水院長も相好を崩している。
 暖だんのスタッフ。前列左から、患者・家族総合支援センター長の灘野成人先生、社会福祉士の福島美幸さん、看護師の池辺琴映さん。後列左から事務担当の藤岡知代さん、同じく松岡順子さん、受付の大鍋由美子さん、看護師の橋本裕子さん
暖だんのスタッフ。前列左から、患者・家族総合支援センター長の灘野成人先生、社会福祉士の福島美幸さん、看護師の池辺琴映さん。後列左から事務担当の藤岡知代さん、同じく松岡順子さん、受付の大鍋由美子さん、看護師の橋本裕子さん
●ウィッグやマンマ製品の展示室も
四国がんセンターでは、がん相談支援センターは病院棟にあり、治療、経済、心など患者や家族のさまざまな相談に乗る。これに対し、暖だんは別棟で、いつでもくつろげるサロンであり、セミナーやイベントを開く学びの場である。治療や就労の相談も受ける。どちらも四国がんセンターで治療を受けていない人も利用できる。

病院棟から独立している暖だん(右)。地域医療連携研修センターも同じ建物にある
暖だんは、もとは駐車場だった土地に立つ。3階建て。1階はピロティーで、3階はミーティングルームや交流室など。
メインは2階だ。木目調の壁。開放的な空間に、入口から順に、学びのひろば、キッズスペース、憩いのひろばと続く。憩いのひろばには、テレビや電子ピアノ、マッサージチェアが置いてある。キッチンコーナーも併設され、紙やプラスチックではなく、ボランティアの人たちが持ち寄った陶器のカップが並ぶ。
地元の砥部焼のアート、地元の書家が書いた「夢」という文字の色紙、患者が撮った病棟からの風景写真などが飾ってある。奥へ進むと、ウィッグ展示室兼相談室、マンマ製品(乳がん手術をした人向けの補正下着、人工乳房など)展示室、ベビー休憩室も備えている。
学びのひろばの書棚には、がん関連から一般書まで約1200冊の本がある。本や新聞を読んだり、憩いのひろばで女子会のように盛り上がったりする人たちもいる。受付の大鍋由美子さんは、室内で流す音楽のリクエストにも応える。全体に家庭的な雰囲気が漂う。
 手前が学びのひろば、奥が憩いのひろば
手前が学びのひろば、奥が憩いのひろば
●準備室のメンバー4人で全国各地を視察
暖だんは、2015年6月にオープンした。準備室ができたのがその1年前で、社会福祉士の福島美幸さん、病棟経験が豊富な看護師の池辺琴映(ことえ)さんら4人が配属された。
この時点で決まっていたのは、「独立した建物で常設のサロンをつくる」ということだけだった。池辺さんが語る。
「当時、遠方から来る患者さんや家族の宿泊施設『向日葵』(ひまわり)で患者サロンを開催していましたが、常設ではなかった。がん治療は外来が中心になり、治療成績が上がるにつれて治療期間も長くなっています。しかし、院外の支援は難しい。だからこそ、いつでも誰でも気軽に来られて、出会った人たちが情報交換したり、気持ちを共有したりする場が必要なのです」
準備室のメンバーは、全国各地を視察した。複眼的に見るため、複数の職種の人で行くようにした。慶応大学や順天堂大学の図書館を視察した際には、地元の愛媛県立図書館の充実ぶりを教えられた。東京で行われた就労に関する報告会では、知り合った厚生労働省の担当者にハローワークの出張相談を頼み込んだ。

ウィッグの展示室。爪をケアする製品などもある
ウィッグやマンマ製品の展示にあたっては、いろいろなメーカーと、「展示だけでなく定期的に出張してアドバイスしてくれること」を交渉した。
病院がここまでやる必要があるのか、という批判が院内から出ることもあったが、くじけなかった。それができたのは、さまざまな患者の声を聞いていたからだろう。
就労では、「副作用がひどいので仕事を辞めようと思う」「お金がないので、1回抗がん剤治療をパスしたい」などと、診察時に切り出せずに数日後に電話で話す患者が複数いた。就労に不利にならない診断書を書いてもらう術もわからない人が少なくない。
外見ケアでは、たとえば、抗がん剤の副作用で爪が黒ずんだ30代の女性患者が「こんな手では買い物にも行けない」と訴えて、院内でも個室に入ることを希望したことがあった。営業に行けない、仕事の意欲が薄れ内向きになる、言われなくても爪を見られた気になる……といった繊細な気持ちに触れることが多々あった。
●笑いヨガ、夏休みキッズ探検隊、トイレにはコンドーム……
こうして誕生した暖だんでは、現在、次のようなケアが実現している。 ①患者、家族、ボランティアらが集える ②図書やセミナーなどを通じた情報発信 ③語り合い、体験型、がん哲学外来などさまざまなイベント ④がん患者を家族に持つ子どもたちの支援 ⑤就労支援 ⑥外見関連の支援 ⑦患者および家族の性に関する支援
①では、地域のボランティアの存在も欠かせない。年に1回のイベントに力を貸してくれる人もいれば、抗がん剤の副作用ケアの帽子を縫ってくれる人もいる。
③の催しは、フラワーセラピー、アロマセラピー、書道教室、歌声ひろばなど年間で130にも上る。
興味深いのは、笑いヨガ(インド発祥で、笑いの体操とヨガの呼吸法を組み合わせた健康法)、タクティールケア(スウェーデン発祥で、講師がタッチすることで不安を和らげる)など、「認知症のケアで活用されている」(池辺さん)ものを積極的に取り入れていることだ。笑いヨガは定員をオーバーする人気だという。
ユニークなのは④だ。臨床心理士を中心に始まった。小学校3年生から6年生を対象に「夏休みキッズ体験隊」と題した1日のプログラムを行う。定員は12人(実際には15人ぐらい)。親ががんであると知っていることが参加の前提だ。
1時間目はがんの学習。小学生ぐらいだと、「家族ががんになったのは、自分がいい子にしていなかったからだ」「がんはうつる」といった誤解もあるので、それも解きほぐす。
2時間目は、心と体についての学習。「心の中で大丈夫と言いながら息をはくと、だんだん気持ちが落ち着く」といった具体的な方法を教えたり、ストロング・ボックスを作ったりする。ストロング・ボックスとは、箱の外側に「好きなこと」「楽しいこと」などを書き、箱の中に悲しみや不安などを書いた紙を入れるものだ。
その後は昼食に病院食を食べて、抗がん剤治療の様子や放射線治療の機械を見たりするほか、緩和ケア病棟や庭も見学する。池辺さんが語る。
「家族に何か起こっているけれど、子どもは教えてもらえない。それは不安で、トラウマになります。話してもらえれば、気を遣うにしても、子どもの表情が変わる。親子のコミュニケーション促進になり、暖だんで一緒にウィッグを選んだりしています」
年に1回ではもったいないという要望を受けて、2018年12月には子どもたちだけのクリスマス会も開いた。両方に参加した、母が乳がんという小学校5年生の男の子は「特別やないやん」と明るくなった。それを見た母が「こんな楽しそうな子どもを見るのは久しぶり」と笑みを浮かべたという。
⑤では、「ちょっと待って!! 今 辞めないで その仕事」と書いたカードを作成して、暖だんのみならず、診察室はじめ院内の各所に置いてある。
⑥のウィッグやマンマ製品の展示室は、倉庫の予定の場所にできた。試着もできるし、カタログ類も多数置く。メーカーのアドバイザーが定期的に来てくれることで、以前は大阪、名古屋などに自腹で出向くほかなかった患者さんの負担がグッと減った。
⑦は、見過ごされがちだが、大切なテーマだ。暖だんのトイレには、コンドームや潤滑ゼリーが置いてある。性の相談案内の冊子も準備している。「医療者が認識するきっかけにもなった」という。

「辞めないで その仕事」のカード。一緒に考えることを呼びかけている
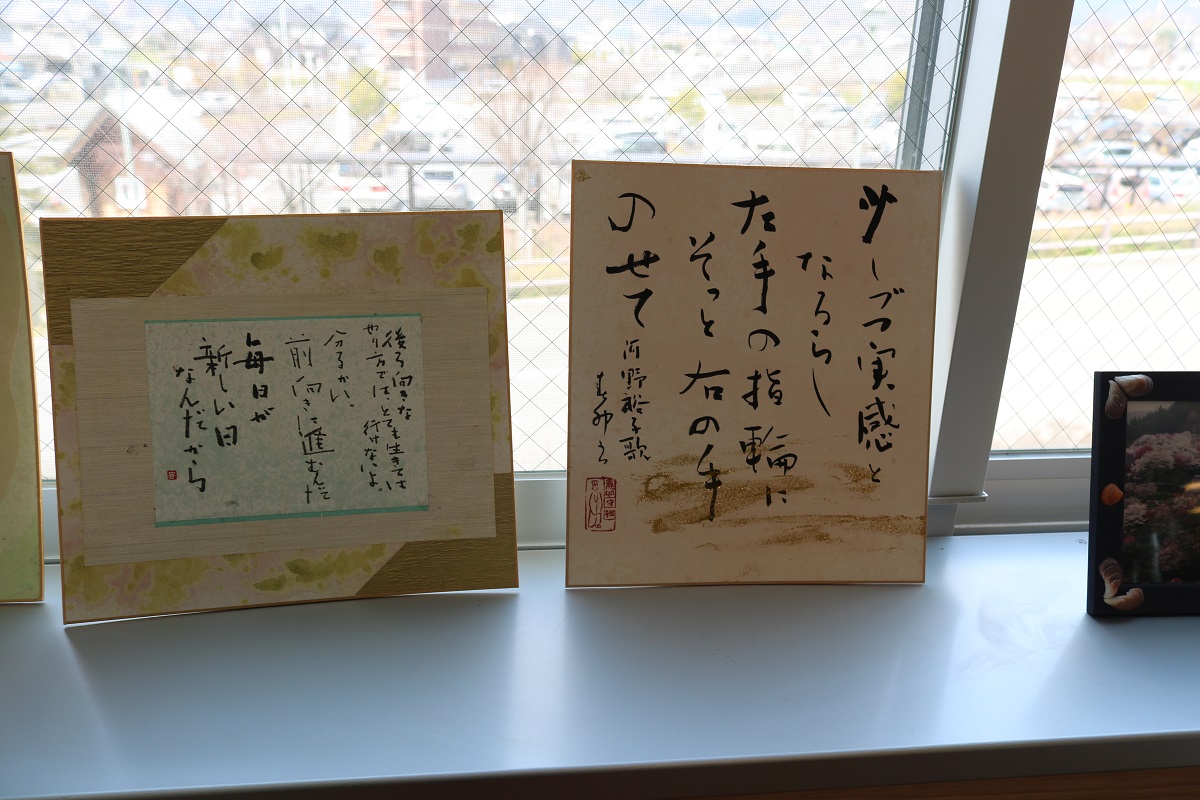
憩いのひろばの窓際にはこんな色紙なども並ぶ
●健康な心は、つらさとうれしさを同時に持つ
私が訪れた日は、憩いのひろばで、午後1時半から外見セミナーがあった。
開催を案内する全館放送が流れる。会場には、ウィッグがずらりと並び、爪などをケアする製品も準備された。
講師は乳腺外科医の清藤(きよとう)佐知子先生と、がん化学療法認定看護師の岸田恵さん。清藤先生が、最初にこんなふうに語りかけた。
「悩んだり不安に思ったりは当然のことです。健康な心は、つらいこととうれしいことを同時に持っているもの。前向きに明るく、という努力を無理にされず、起こったことにできる範囲で対処していただければと思います」
それから、具体的な話に入った。人間の髪の毛は約10万本と確認してから、「髪の毛が抜ける前に髪を切るといいです。短いほうが楽ですし、あらかじめウィッグに合わせておけば、急に髪型が変わって、事情を知らない人に『髪切ったね』と言われて複雑な気持ちになることもありません」
ウィッグには、100%人間の毛を使ったものも化学繊維のものもある。価格は数千円から数十万円と幅広い。違いは見分けにくく、参加者の一押しは6800円のウィッグだった。
「値段は、見た目やかぶり心地とは関係ありません。大切なのは、試着して、自分が似合うと思うものを堂々とかぶることです」
風で飛ぶことはない。気にしているのは本人だけで周囲は気づかない。帽子や手ぬぐいを活用してもいい。付毛がある帽子なら、ちょっとコンビニに行くときなどに利用しやすい。いくつかのウィッグを気分で替えている人もいる……。

外見ケアのセミナー。紙芝居で説明しているのが乳腺外科医の清藤佐知子先生、右奥が看護師の岸田恵さん
こうした話に続いて、眉毛の描き方(事前に携帯で写真を撮っておくと位置を間違えない)、肌や頭皮のケアでは「清潔、保湿、刺激を避ける」が大事なこと、爪は薄い色のマニキュアを重ね塗りする、などの対策を伝えた。そして、こう結んだ。
「外見の変化があっても、対処法を組み合わせて、行きたいところに行きやりたいことをやってもらうことも大事だと思います」
講演が終わると、参加者たちがウィッグを手に取る。「今はカツラって言わないの?」と聞いた男性は「地毛よりきれいですよ」と感心していた。これから治療が始まるという女性は「知らないことがけっこうあり、参考になりました」と納得していた。
●暖だんが一緒に土台を築けた
暖だんがオープンして6年近く。
福島さんは、元教師の女性患者から聞いた話が忘れられない。
治療がつらくこもりがちだったが、勇気を出して暖だんに行ったら、ピアサポーターの人たちが「ほんとうによく来てくださった」と迎えてくれた。この言葉に救われたという。彼女は福島さんに「今は笑いヨガのインストラクターの資格を取ろうとがんばっています。患者さんの気持ちに沿えるお手伝いがしたい。それができるのが暖だんという場所です」と熱く語った。
池辺さんは、大腸がんの40代の女性の涙が心に残る。
女性はストーマ(人工肛門)のことで悩み、なかなか就職活動に踏み出せなかった。暖だんで、ストーマを着用しながら働いている人の話を聞いたりした。1年ほど経って、ハローワークに自ら出向いて登録した。登録カードをもらい「やっと社会活動の第一歩を踏み出せた」と涙を流した。暖だんが社会復帰への土台を一緒に築けた。そんな思いがこみ上げたという。

マスコットのだんだんちゃん。好物はプリン、趣味は旅行
患者・家族総合支援センター長の灘野成人(せいじん)先生は2017年に就任した。肝胆膵内科の医長も務める医師である。こう語る。
「私もセンター長になって、診療以外のこういうケアが必要だとつくづくわかりました。医療だけをしていればいいわけではない。医師や看護師など病棟のスタッフは、積極的に暖だんを知って患者さんに伝えてもらいたいと思います」
暖だんという場を通じて、患者のマインドが上がれば、引いてはがんとの共生にもプラスに働くであろう。
●課題は診療報酬ゼロのこと、国は人への手当を
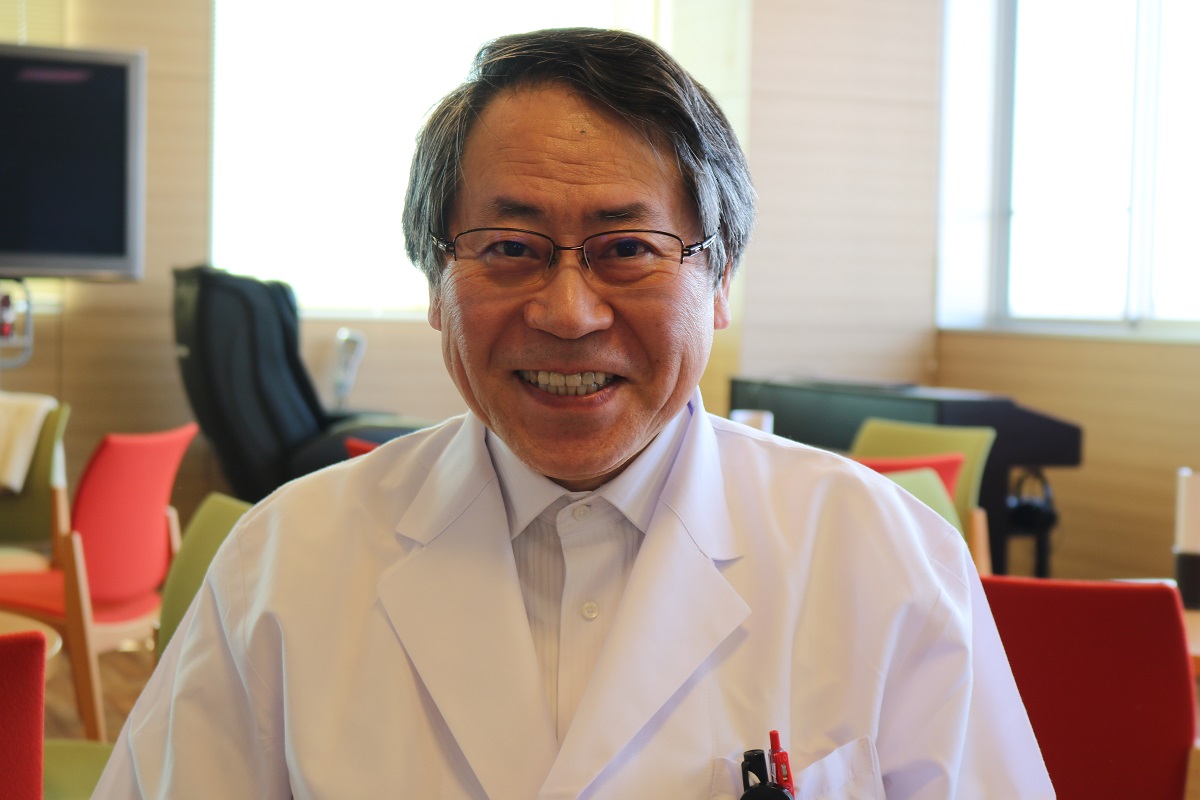
谷水正人院長。緩和ケア外来も担当している。松山市在宅医療支援センターも立ち上げ、センター長を務める
暖だんの生みの親と言えるのが、初代患者・家族総合支援センター長の谷水院長である。立ち上げにあたり心がけたのは、専従組織にすることだ。
「診療の合間に対応する付加業務では、質や継続性、計画性という観点からは難しい。そこで、建物を造り、人を配置しました。そのほうがスタッフも安心して働けます。普通の考え方だと思います。国が定めているがん診療連携拠点病院の要件に則っただけです」
谷水院長はさらりと語るが、わざわざ建物まで造れば、簡単には引き下がれない。しかも、当時は統括診療部長だった自身がトップに就任することで、院内へアピールもした。
今も、がん哲学外来カフェのイベントのときなど、時間があれば暖だんに出向き、患者や家族と言葉を交わす。医師と患者・家族では、ベースとなる理解度が異なるので、ときに病院への恨み節も出るが、会話は楽しいし、本音も聞けるという。
ただ、暖だんの活動はすべて、診療報酬の対象にならない。行政の補助もいくらか出るが、基本的に病院の持ち出しとなる。病院の評判がよくなれば結果的に患者数が増えるかもしれないが、経営面の課題が残ることは否めない。
「拠点病院の機能として必要なのに、手当が不十分。ここが問題だと思います。国は、研究費や医療機器には補助を出すのに、人件費にはお金を付けません。でも、医療は人の仕事なのです。人を大事にしなければ、継続が難しくなる」
と谷水院長。暖だんがさらに発展したり、似たような施設が全国に広がるには、経営面の課題をクリアしなければならない。やる気のある個人に負担がかかったり、担当者によって充実度に差が出てしまっては、続かない。
訪れた日の夕方、キッズスペースのマットで飛んだり跳ねたりして、おばあちゃんと幼い孫2人が遊んでいた。そこへ抗がん剤治療を終えたお母さんが来た。
「はい、帰るよ。自動車の中でお菓子食べよう」
もっと遊びたいらしく、ぐずる子どもたち。まるで保育園のお迎えのようだ。3代の家族は、名残惜しそうに、仲良く帰って行った。



 【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ
【重要】がん患者・家族のSNS「サバイバーネット」サービス終了 のお知らせ 2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定
2025年度「がんアドボケート活動助成事業」助成対象の3つの活動が決定 クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え
クリコの「今日をささえる」レシピ/第1回 ポムピン・サワーディップ添え 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性
村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第23回 改めて考える「対話」の重要性





